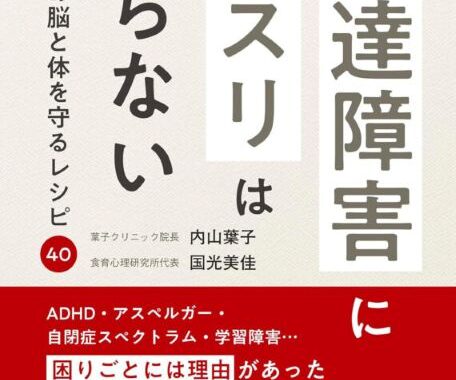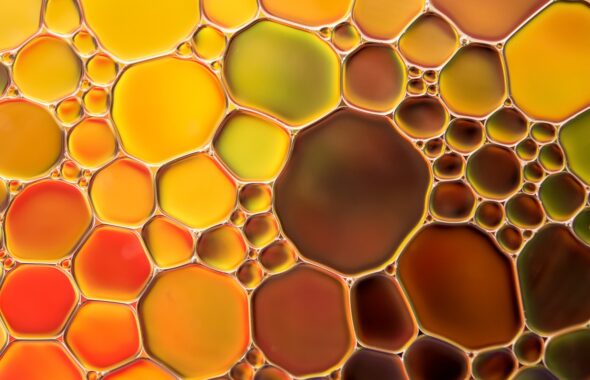さつまいもの脅威の基腐れ病の現状と対策
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.69
2026年1月 業務執行理事 南埜 幸信
サツマイモ基腐病(もとぐされびょう)が急速に全国へ広がっている。日本でその発生が確認されたのは2018年秋からで、鹿児島県および宮崎県において、サツマイモの株が立ち枯れ、塊根(イモ)が腐敗する症状が多発し、収量の減少が深刻な問題となっている。沖縄県のサツマイモ産地でも同様の症状が認められており、これら3県では、国内ではそれまで発生報告のなかったサツマイモ基腐病(以下「基腐病」という)が発生していたことが明らかになった。本病は、2020~21年秋冬には熊本県、福岡県、長崎県、高知県、静岡県、岐阜県、2021年夏以降には群馬県、茨城県、東京都、千葉県、岩手県、愛媛県、福井県、埼玉県、山形県、石川県、北海道でも発生が確認されている(2021年8月31日現在)このように、基腐病は急速に全国へ広がっている。広域的な感染拡大は、主に基腐病菌に感染した種苗の移動により生じる可能性が高いと考えられる。
基腐病は、Diaporthe destruens(ディアポルテ・デストルエンス)という糸状菌に感染することにより、苗床や本圃で発生する。貯蔵中の塊根にも発生する。基腐病菌は、主に、感染した種イモや苗を植え付けることで圃場に持ち込まれる。圃場で生育不良や萎れ、黄変、赤変などした株の地際のあたりが暗褐色~黒色になっていたら基腐病の可能性がある。本病の病変部には微小な黒粒が多数形成され、水に濡れるなどすると、そこからおびただしい数の胞子が漏出し、これらの胞子は、降雨により生じる停滞水や跳ね上がりなどにより周辺株へ広がり、基腐病のまん延を引き起こす。株元以外の茎でも、畝間の汚染土壌や周辺株の病変部、水で移動した胞子などに接触すると感染し、発病すると考えられる。本圃で茎葉が繁茂する生育旺盛期は、株の異常に気付きにくいため、発病が密かに進行する。そのため、収穫期が近づき茎葉の生育が衰える秋頃になって一気に枯れ上がったように見えることが多い。株の地際が感染すると、地下部の茎、しょ梗(茎と塊根をつなぐ部分)、塊根へと病徴が進展するため、塊根はなり首側から褐色~暗褐色に腐敗することが多い。また、収穫時には健全に見えた塊根が貯蔵中に発病し、腐敗することもある。収穫後は、圃場の罹病残渣中で病原菌が生き残り、次作の伝染源となる。発病株が少ないと、基腐病の発生に気付かないまま栽培を繰り返し、種苗や圃場の土壌の汚染が急速に高まる可能性がある。そのため、1年目はわずかな発病であったとしても、何も対策をとらずにいると、数年後には激発して収穫皆無となる恐れもある。
2018年にこの病気が鹿児島県を中心に南九州で発生して以来、効果のある対策が打てないまま今日まで経過し、さらにはその拡大が進行している。対応できる農薬が無いというのが、その根本的な原因である。関東でも茨城県では、2025年には、20ヘクタールを超える圃場に被害が拡大し、県の指導として、発生圃場については、2年間はサツマイモの栽培を止めるようにという指導が出ている。
つまり、畑に持ち込んでしまったら対策がなく、サツマイモそのものの栽培ができなくなるということになるので、特に有機農業でサツマイモを栽培されている生産者にとっては、経営の柱に直結する重大な問題である。茨城県はサツマイモ王国と言われるように、適地が多く、古くからサツマイモの栽培が盛んな地域である。生食用としての出荷に加え、干し芋加工、水あめやデンプンの原料加工、菓子や餡の原料となるペースト加工、焼き芋や大学芋などの加工品生産まで、多くの加工メーカーが関わる一大サツマイモ産業が農業の基軸となっている県であり、有機加工食品への影響も極めて大きい。
そこで今月の31日に、下記の通り茨城県のつくば市にあるつくば国際会議場で、地元の有機農業技術研究会と一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアム、茨城大学等がコラボして、この基腐病の有機農業での対策について、多くの知見と経験のある方々からお話を伺えるようにセミナーを開催することにした。鹿児島県では、長年有機農業を実践してきた圃場において、基腐病が発生していないという報告もある。原因は糸状菌という土の中にある土壌菌ではあるので、むしろすべての生き物が共生できる土壌の熟成ということで、天敵も害虫も無い世界の有機農業の技術しか、この病気に対応することはできないのではないかと考えている。土壌消毒で病原菌をはじめすべての生き物を殺すという現代農業の先に、解決策があるとは思えない。
年明けに全国の有機生産者に本セミナーの案内をしたところ、地元関東だけではなく、九州など各地の生産者やから参加希望の声が多く届いてきた。まさに時を得たテーマなのだろうと、現場での事態の深刻さを憂うとともに、この問題の解決でオーガニックの取り組みをさらに広げる結果につなげていきたいと考えている。

次号に続く