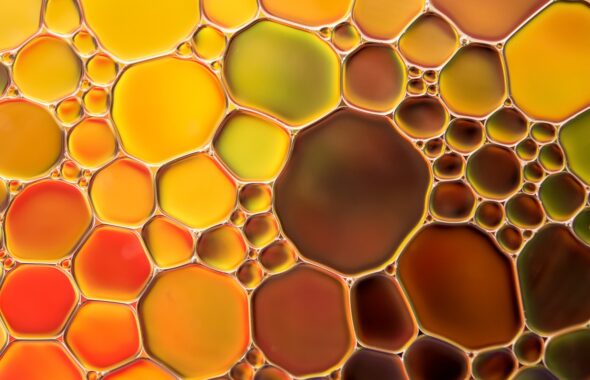有機米の再生二期作とスマート農業技術
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.44
2025年6月 業務執行理事 南埜 幸信
42号で、今年から加工用の有機米の新たな確保のために、再生二期作に取り組むという話をさせていただいたが、実はこの技術には、最近農業界でも注目され、農林水産省からも多くの補助事業が展開されている、いわゆるスマート農業技術の活用が求められてくる。特に予想されるのが、再生二期作の取り組みにあたって、特に二番果の収量を大きく左右するであろう、二番果向けの追肥をどのようにするかという課題と、収穫終了後の田んぼの状態を細かくセンシングして、再生二期作を実施するか中止するかという判断を、圃場の水分状態と残った株の状態で即座に判定していく技術である。
まず一番目の課題。二番果に向けた追肥であるが、理想は一番果の収穫の約二週間前が、最も効果的であるという農研機構の中野先生の研究成果から、その理想とする時期に追肥したいのであるが、当然稲のほうは登熟期の真っただ中。田んぼに入ることは厳禁の時期である。そうなると追肥は、ドローンを使うという選択肢しか無くなる。つまり、ドローンを使った追肥技術が必須となる。今年は費用対効果もみたいので、すべての圃場で追肥をするのではなく、追肥区と無肥区を設けて、比較実験をする予定だが、明らかに追肥効果が高いということになれば、再生二期作にはドローン追肥が必要という条件か出てくる。これをまず、今年の備えとして準備していきたい。当然将来の機械導入を視野に入れたなかてある。
次の課題は、収穫後の田んぼの状態のセンシングである。つまり、田んぼの水分状態によっては、コンバインの作業時に、田んぼに大きな轍を作ってしまったり、土をコネったり等で、二番果が期待できる正常な切り株がどの程度残っているかという診断である。この時点で切り株が正常に残っていないということであれば、再生二期作の対象圃場から外し、直ちに秋耕を実施し、粗大有機物の分解促進をはかり、翌年度の稲作に備えたほうがはるかに効率的である。つまり一番果の稲刈りが終了後、すべての圃場を速やかにセンシングして、再生二期作に移行する水田と、中止する水田の仕分けの技術である。
これらの重要課題を改めてテーブルに乗せたときに、これは、スマート農業の技術に詳しいチームとのコラボである。さっそく私のネットワークで検討いただいた結果、この事業全体について、スマート農業についての農水省の補助事業の対象としていただくチーム編成と、事業計画を明確化し、できれば今年の農水省の公募に間に合わせたいということになった。6月中の公募締め切りということで、かなりの企画構築スピードが要求されているところだが、それに十分対応できる可能性があるチーム編成ができた。キーになるのは一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムに最近入会いただいた、株式会社ニューグリーン様だ。このスマート農業の補助事業は、基本的には需要側からの要請という申請要件が求められていて、有機米を可能な限り広げていくというニューグリーン様の事業にはピッタリはまってくれた。再生二期作のコメは、カメムシの食害等の品質的な課題があり、そこが初年度としては、現時点で需要側を纏めていくということはかなり難しいと感じていたし、現状の一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの実力としては、このリスクを受けていくのは難しいと判断していたところであるが、ニューグリーン様は収穫されたものは全部受けるという判断をいただいたので、本当に感謝している。ちなみにニューグリーン様は、私の出身大学のプロジェクトである、あいがもロボットの普及拡大にも取り組む、有機でのコメ作りのパイオニア企業でもある。この決断に、名古屋大学農学部を主軸とする農業研究機関である、名古屋産業研究所。そして、ドローン技術の最先端のノウハウとネットワークを持つドローンジャパンさん。そして、三重県の注目の有機米生産法人の辻農園の辻社長が連携いただくことになり、この再生二期作の実現に向けた本気の取り組みが始められると感激している。
農林水産省は、今年のコメ不足による価格高騰を抑えるために、今後、輸入米の拡大を急ぐとの報道が入っている。特に備蓄米に輸入米を使うということのようだ。日本の主食であり、減反政策でコメを作らないようにしてきた農水省が、いきなり輸入米を増やすという決断である。私たちは、国産のコメを守り育てたい。主食のコメを輸入に頼るというのは、絶対にやめさせたい。国内のコメ農家を弱体化させてきて、ここで輸入米というのは、政策として納得できない。しかし、反対だけしていては、なにも変わらない。この再生二期作の取り組みによって、国内でコメは十分今年の秋から増産できる。田植えも除草も不要で、単位面積あたりの収穫量を2割~5割増やすことが可能になるかもしれない。
これが実際に実現できるかどうか。今年の夏は暑い夏になりそうだ。
次号に続く