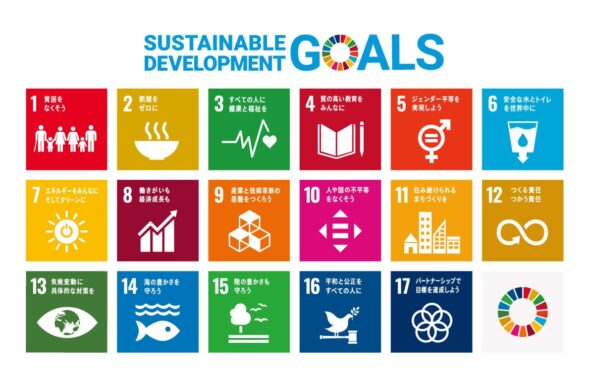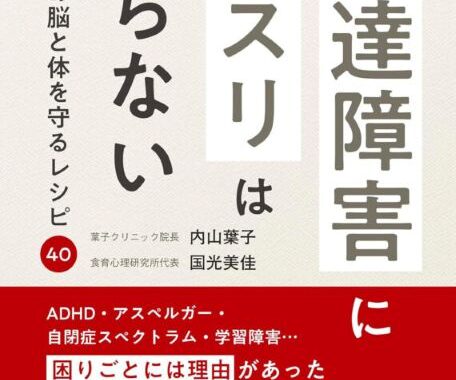関東地方における大豆の有機栽培マニュアル
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.58
2025年10月 業務執行理事 南埜 幸信
先月の埼玉県での有機栽培技術研修会と、今月の茨城県での有機栽培技術研修会と、両方で、農研機構の有機研究グループ長の田澤先生から、関東地方での有機大豆の栽培体系について、詳細な最先端の栽培技術についてお話を聞くことができた。大豆については、結構地方により適性品種や播種時期が異なるので、あくまで関東地区での限定の内容ではあるが、その考え方は全国の有機大豆の生産指針にもつながるものではないかと考える。当日視聴できなかった方のために、私のメモで申し訳ないが、下記に要約して皆様にお伝えしたいと思う。詳しくは農研機構の標準作業手順書(SOP)として公開されているので参考にしていただきたい。【農研機構SOP】で検索いただくとアクセスできるのでぜひおすすめしたい。閲覧には会員登録が必要だが無料なので安心してほしい。大豆の有機栽培で大事なポイントの一つは、圃場準備である。特に水はけが悪いと生育が滞るので、暗渠や明渠などの事前準備をお勧めしたい。
次に品種選定であるが、中生・晩生の小粒~中粒がお勧めである。それは、小~中粒品種は鞘の数がもともと多いことから、少し実入りが悪い鞘がでても、それをカバーできるだけの収量を得ることができるからである。加えて、在来の大豆品種は晩生であることが多くこれが、晩生品種が有機栽培に適するといわれている理由にもなっているといえる。
次に大事なポイントは、可能な範囲で播種時期を遅くずらすことである。最近の夏の猛暑と干ばつの条件下では、播種時の土壌水分の確保の配慮は必須ではあるが、播種を遅らせるということは、開花時期を遅らせるということになり、開花時期が遅いほど害虫の被害が軽減されるのである。農薬を使えない有機栽培では重要なポイントになる。
次のポイントは、早期の中耕培土の実施である。播種後10日~2週間後、本葉1~2葉期に実施し、子葉が埋まる程度にしっかり培土して、株間の雑草もしっかり抑えることを狙いに実施したいということである。そのためには、発芽の揃いも大切で、そのためにはアップカットで砕土率を高めるとともに、畝立て播種により湿害を回避すること。播種時の土壌水分の確保のために、耕耘から播種まではなるべく間をあけないということが大切である。つまり、除草の前の抑草という考え方が大切である。
次に有機大豆栽培で問題となる害虫について、まずダイズシストセンチュウは、大豆の長期連作により発生リスクが高まることから、輪作を基本に、抵抗性品種の導入と、対抗作物との輪作も大切な技術である。まずは、ダイズシストセンチュウの発生のない圃場を選定することが大切である。
ハスモンヨトウはBT剤で対応可能であるが有機栽培では発生は少なめである。ハダニも有機栽培では発生が少ない。ともに天敵の効果があるのではと言われている。カメムシ類の対策については、播種時期を遅らせることで対策になるのではと期待している。慣行栽培では農薬に弱いということで問題にならないマメハンミョウは有機では問題になることが考えられる。今後の対策が必要と言われている。
大豆の土壌病害については、茎疫病と黒根腐病がある。これらは、大豆の長期連作と、土壌水分の高い条件で発生するリスクが高まる。マメシンクイガ対策としては、有機で認められている銅剤系の資材と、BT剤の利用が効果が期待できる。いずれも、遅く播種することで、かなり回避できると考えられる。
有機農業は長く国や研究機関から相手にされず、研究対象にもでてこなかった。しかし、今回の農研機構のしかも有機グループ長の話を聞いて、時代が大きく変わったことに感激している。有機農業が次代の農業技術の柱として、国の最高峰の研究機関で技術研究が進んでいる。
このような時代が来るとは思っていなかったが、ぜひこれからは、国や都道府県の研究者と一体になって、有機農業の栽培技術の向上に拍車をかけていきたいと考えるところである。
次号に続く