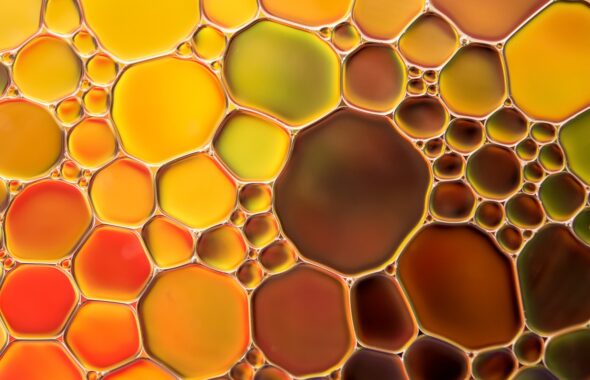日本学術会議公開シンポジウム Soil Healthとは
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.50
2025年8月 業務執行理事 南埜 幸信
先週末、日本学術会議主催の公開シンポジウムがあり、まさしく表題の土の健康Soil Healthをテーマに日本を代表する多くの土壌学者や農学者が集合し、まさしく圧巻の講義が続いた。
まず、「土の健康」というテーマを置いた以上、現代の農学者の多くは土は単なる物理的な物の集合体ではなく、まさしく総体として複雑な生命系を持つ、まさしく生き物として機能する、生きている存在を前提としているということを証明している。この考え方になっている以上、土は単なる植物の根を物理的に支えるものではなく、生き物としてとらえるというオーガニックの基本的な理念に統合される。そして生きている以上、成長もあり、退化もあり、健康もあり不健康もありということになる。
私が約48年前に、有機農業の研究をしたいという夢を持って、生態学的な農業へのアプローチをするということで始まったばかりの東京の農学部に入学したオリエンテーションで言われたこと。土壌微生物と有機堆肥と生きている根との共生で有機農業の研究をしたいと話したら、植物は有機物を吸収できないのだから、有機農業は合理的ではない。化学肥料を土壌に合わせて施肥設計して投入していけば農業は成り立つものだ。有機堆肥の施用など無意味といわれた時代からは、隔世の感がある。日本を代表する日本学術会議の研究者たちが口を揃えて、土は生きている。従って土の健康を保つことが、農業の最大の目標なのだという時代。本当に生きていてこのような時代を迎えることができたこと、感謝以外にない。
そこでシンポジウムの中身である。土の健康という概念をまず定義することと、その健康度合いを判断していく指標の設定がテーマとなる。その意味では、これから先は、私たち人間の健康と対比して整理していったほうが分かりやすいので、そのように話を進めたい。ひとつ大きく違うのは、土の健康度合いは、土単独で測られるものではなく、その生きている土と共存し、共生し、会話して育っている作物の健康度合いも含めて考えている必要があるということになる。私たちも健康診断(人間ドック)で自身の健康状態を調べるときには、まず血液検査をする。血液の中の健康の指標といわれる成分を化学的に分析して、基準値と照らし合わせ異常がないかとチェックする。土の場合も、植物を育てる養分がバランスよくかつ過不足なく含まれているかというチェックである。この過不足なくバランス良くというのが大きなポイント。人間も栄養やカロリーが多いから健康ということにはならない。むしろ栄養の採りすぎはメタボや糖尿病など病気症状に至ってしまう。土壌養分をバランスよく過不足なく。これは実は人間にはできない。水耕栽培でも不可能であろう。生きている世界の天文学的な多様な役割を持つ生き物の共生によって、バランスよく過不足なくというのは達成されるのである。人間の健康もそうである。健康=栄養をたくさん取ったではないのだ。過不足は生命活動のバランスを崩し、病気や免疫機能の低下を招く。多様な生物の調和と繁栄が生き物の世界の定石なのだ。まずは押さえたい土の健康のバロメーター。それは植物の必要な多様な栄養分を過不足なくバランスよく保持していることである。
次に押さえたいポイントは、栄養分がそこにあるからといって、すべてがそのままで植物が吸収できるわけではないことである。根が土の中に広い根圏を形成し、生きている土と根の周りに特に天文学的な数で存在し、根と共生する根圏微生物の仲立ちによってはじめて根は土から養分を吸収できるのだ。特に土が保持している養分を水に溶けるイオンに変え、植物に供給してくれているのは、まさしく根圏微生物である。ちょうど人間の栄養吸収に腸内微生物が重要な役割を果たしているのと同じ。植物も自身だけでは土壌が保持している肥料養分を利用できないのだ。違う言い方をすれば、土の健康度合いとは、いかに多くの根を受け入れることができるかということになる。つまりは、生きている土として、根が入っていける土の柔らかさと、代謝力の高い水分保持力が高いほど健康な土といえるのだ。
従って土の健康度合いをはかる指標としては、土の生物性、物理性、化学性の要素分析からスコアをつけていくことであり、さらには、お医者さんでいうレントゲン検査にあたると思うが、土の断面調査をして、根圏の発達具合を確認していくことである。そして、土の団粒構造の発達と相関関係にある土の養分を保持する力を測り、多様な養分がバランスよく保持されているかどうか。これらの総合指標から土の健康度合いのスコアは確定していくのだ。
次号に続く