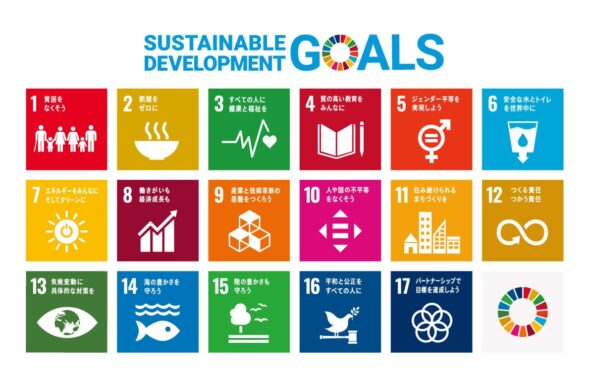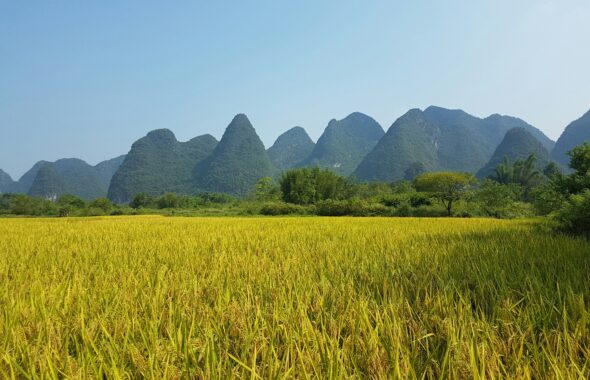学校給食への有機食材の安定供給について
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.59
2025年10月 業務執行理事 南埜 幸信
10月2日~4日に東京の浜松町で開催された、オーガニック・ライフスタイル・エキスポの事務局から、一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの佐伯専務に、今回のコープ自然派兵庫と泉平さんと、コンソーシアムの三者協定で、兵庫県の学校給食への有機冷凍野菜の供給開始について、セミナー枠を設けるので話をしてほしいという要請があった。オーガニックビレッジ等で地域の学校給食(公共調達)に有機食材をという声が強くなっていることから、全国に水平展開できるようなモデルにという可能性があるのなら、ぜひ披露してほしいということであった。
通常の有機野菜ということであれば、当然佐伯専務の専任事項なので、佐伯専務にお話をいただくことがベストと思われるが、エキスポの事務局から、今回の三者提携が国産の有機冷凍野菜を柱とする取り組みであったことから、この任に当たってきた私からお話をさせていただくことになった。
実は私の学校給食へ有機野菜をという取り組みは、1990年代の中ごろの、まだまだ有機農産物が、ガイドライン表示でやっと市場にヨチヨチと出回り始めたころからになる。そういった意味では、はるか以前からの先駆的な取り組みに関わらせていただいたことになる。
このきっかけは、当時オープンマーケットに有機農産物をということで、有機農産物の卸売りの専門企業を立ち上げ、量販店はもちろん、全国の有機農産物を欲しいという各種企業や団体に、全国の有機産地(当時はガイドラインによる有機)からの物流を集約し、全国の希望する企業や団体に提案供給を本格化させていた時代で、その取引先の一つに、大阪にある、クリスチャン系の有機宅配販売組織の、(株)大阪愛農食品センターとの出会いがきっかけであった。この組織は当時から、大阪府下の茨木市と高槻市の学校給食会からの要請で、学校給食への有機農産物に取り組んでいたのである。
品目提案は学校給食会の主体メンバーである栄養士さんたちが、次月の献立を作成した以降、必要な品目と数量を提示し、月一回の入札を経て、採用が決定されたら、指定の給食業者から注文が入り、約束の数量を約束の価格で、しかも欠品なく納品するという大きな責任の下に運営をされていた。この事業の前提として、これらの自治体が、学校給食について、自校方式で取り組んでいたため、比較的原料のような形で有機野菜を納入しても、下処理をして調理まで貫徹することができる体制であったことも大きな要素である。もしこれがセンター方式であったら、短時間で大量の調理をこなす必要があることから、土がついている素材野菜などは、おそらく納品は無理であったことから、有機の取り組みは生まれなかったと思う。つまりは、栄養士さんたちを取りまとめていただく組織のリーダーシップと、それを入札という価格決定のなかで、欠品無く納品できるという流通チームの両輪が、上手に連携して、潤滑油たっぷりの歯車を回すことができ、素材から料理までを、短時間でこなすことのできる機能を備えた調理場が揃わったがゆえのことだと思う。
実際の入札に参加してみて、まずは、欠品ゼロという前提に立った時に、どうしても提案できる品目は、収穫後にある程度の期間のストックが可能で、自然に在庫として保持できるものでないと、なかなか提案ができなかった。つまり、米とか芋類とか、たまねぎや、冬場の根菜類等、ストックの可能な限られた野菜を限られた時期に納品することが精いっぱいであった。ほうれん草や小松菜、キャベツ、ブロッコリーなどの鮮度維持が難しいものはまず提案できないというかなり萎縮したものであった。また、独特な発注単位として、ぶどうは粒数であるとか(生徒一人当たり○○粒×生徒数)、ジャガイモもSサイズだけほしいとか(生徒一人当たり○○個)、普段スーパーや量販店に提案納品するのとは、全く違う発注単位に驚かされるとともに、これは絶対に青果納品の延長には考えられないということ等である。
またさらには、青果を栽培すると、特に果菜類や葉菜類などは、毎日収穫・毎日出荷が基本であるところ、給食のように、一か月のなかでも、献立に入る日は大量の発注があるが、献立に入らないと発注がゼロということには、生産者も流通もとても対応できないであろうということである。私などは当時、日々の発注でこんなにブレると、とても欠品なく納品は不可能であるので、月ごとの入札ではなく、いっそのこと、作付け時点で入札して、全量買い取りという仕組みを動かしていただきたいと要請したくらいである。ましてや野菜には当然旬がある。ハウス栽培が進んだとしても、昨今の夏場の異常高温と干ばつの中で、有機の生鮮野菜を、不定期で欠品無く一か月納品し続けるということは、有機の生産者にはお願いできるはずがないのである。
学校給食がこのような課題を抱えているのに、学校給食に有機野菜をと。特に地元の有機野菜をということを強引に進めていくと、生産者も調理現場も破綻してしまう。これに気が付き始めたところから、今回国産有機冷凍野菜を学校給食に採用することにより、有機食材がもっと安定的に欠品無く、調達できるのではないかということを、全国オーガニック会議の学校給食の検討部会の方々が気が付き始めたところで、今回の講演要請になったと考えている。
付け加えると、来年から学校給食が無償化されることで、給食の原価低減圧力が上がり、さらに食材調達が厳しくなると予想されるところ、はたして有機農産物の利用は進むのかという疑問である。この点今回のセミナーで、給食の原点は「福祉」ではなく「教育」であると再認識をしたいとお伝えしてきた。義務教育に農業教育を取り入れ、学校給食に有機食材を利用拡大していく政策と、有機農業を中心とする農業教育を食育のど真ん中にして進める政策を、車の両輪として進めてほしいものである。
次号に続く