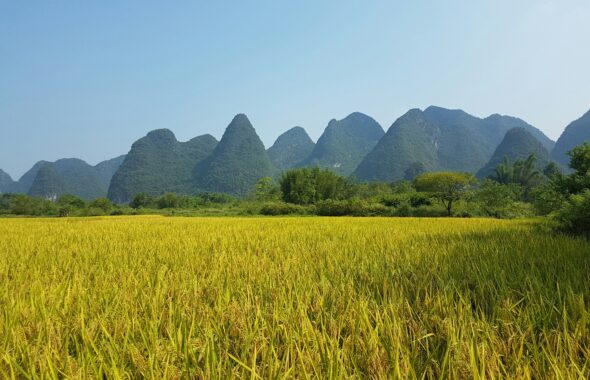コメの再生二期作勉強会の開催報告
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.49
2025年7月 業務執行理事 南埜 幸信
以前このブログで、農研機構の再生二期作の取り組みについて、日本の先駆者である農研機構中野洋先生の研究内容の話と、その実証実験を千葉県の栄営農組合の佐藤真吾さんの田んぼで実施するという報告をさせていただいたが、これを一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムから社会に対して提案発信するということで、今回ウェビナーで公開勉強会を実施した。
折しもアメリカとの関税交渉の協議が、関税15%税率で合意に至ったという取引で、アメリカ産のコメの輸入の倍増と、大豆とトウモロコシ等のアメリカ産の農産物を80億ドル(約1兆2000億円)輸入するという、日本の農業や農地と引き換えに、特に主食含めて穀物をアメリカへの依存度を高めるという譲歩と関税を引き換えにした記念すべき日に実施したことになった。
そもそもこの再生2期作に取り組みたいと考えたのは、一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの多くの加工メーカーから、特に有機味噌やせんべいなどの加工用米を原料にするメーカーの方々から、加工用の有機米を確保したいので、契約できる生産者を探してほしいという要望を受けた。実は、昨年来のコメの価格高騰で、生産者の多くがいわゆるご飯で食べる飯米の生産に集中してしまい、価格の安い加工用米をあえて作るという生産者が激減したことで、有機の加工メーカーの方々か、本当に困ってしまったということがある。特に有機農業の場合、足らないからといって、急に面積を増やして増産するのは本質的に困難を極める。長年の化学肥料や農薬の使用により痛んでしまった土を健全な状態に戻すのは、土づくりという時間をかけた取り組みが必須である。水田を持っているからといって、機動的にスピーディーに拡大するのは無理である。そこでこの、加工用有機米の突然の不足に対応できる方法として注目したのが、今回の勉強会のテーマとなった再生2期作という技術である。面積もそのままで、新たな田植えも必要とせず、一回の作付けで、2回の収穫という、コメ不足をスピーディーに解決できる可能性が高い技術である。
以前にもお話をしたが、夏に一回目の収穫の時に、従来より長く葉と茎を残して、次に実る2番果への養分供給余力を残すことで、充実した2番果を得ることができる。農研機構の中野先生の過去の研究成果としての最高収量は10aあたり1.5トン(日本の水田の平均収量は530キロ前後)という驚異的な収量が得られたこともある技術だ。秋の積算温度の関係で、現状の平均気温の分布から推察すると中野先生は関東以西(北限は宮城県あたり)ということで発表されているが、最近の農産物の作付け状況などみると従来はありえないといわれた北海道でのサツマイモやゴマ栽培がむしろ積極的に進められるようになってきたことからも、地球温暖化の傾向と品種とのベストな組み合わせができれば、少しずつ適応地域が拡大できる可能性があると考えている。
今回の再生2期作の勉強会に出席いただいたメンバーを見ていて驚いたのは、農林水産省や農協の関係の方々の参加が多かったことである。一昨年まではコメが余り、安値が続きという状況分析であったと思われることから、エッジの効いたコメの増産技術には農業行政は関心が無かったのかもしれない。しかし、猛暑のなかでのコメの品質低下や、トータル収量が見えにくい作況指数を前面に出しすぎてきたことによる需給状況の認識不足など、コメの価格高騰という現実に直面したことで、農研機構という優秀な研究機関を下部機関として持ちながら、再生2期作の検討がほとんど行われていなかったのではないかと推察している。
技術的な課題や取り組む地域の限定はあるとしても、この技術は有機米に限らず、日本のコメの生産能力や生産効率を飛躍的に向上させ、つまり生産者にも無理なくコメの生産原価を下げることができ、生産者にも消費者にも、そして加工メーカーにも、日本全体に与えるメリットはかなり大きいと思える。
トランプと自動車業界の圧力で日本農業の生産能力向上への取り組みを放棄し、アメリカからの農産物を増やしていく前に、やるべきことはたくさんあるように思う。貴重な生産者と農地を失くしてしまう前に、いま我々がどのような行動を起こすか。これが問われていると思う。
次号に続く