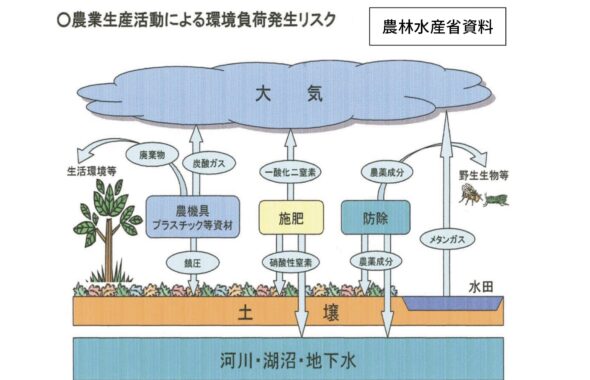茨城県のNPO法人友部コモンズの有機農場との連携
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.45
2025年6月 業務執行理事 南埜 幸信
茨城県の笠間市にあるNPO法人友部コモンズは、生物多様性豊かな環境再生や、地域の有機生産者との連携で地域社会を持続可能性のある姿に変えようと取り組んでいる法人である。お金や利益最優先の価値観が環境を壊したり生きづらい社会をつくっているんじゃないかという考えから、そこから少し距離を置いてお金に頼りすぎずに、生活に必要なものをできるだけ自分たちでつくってみようという試みに取り組んでいる。
食べるもの、住むところ、着るもの、エネルギー。一人ではできないけど、仲間と一緒ならできることがある。支え合いのコミュニティの中で、お金ではなく仲間に頼れることがある。そして、そうやって生きるためのインフラをつくる中に、たくさんの仕事が生まれ、多様な人や才能を活かせる場所が生まれる。生きるスキルが積み上がり、それが生きる自信になっていく。仲間との協働が支え合いをつくっていく。そんな積み重ねが回りまわって、環境や地域に良い影響をもたらしていく。友部コモンズはそんな未来を目指している団体だ。そのなかでも特に柱にしている事業が、有機農場の運営。茨城県有機農業技術会議にも参加し、茨城大学の小松崎先生の有力なブレーンでもある。実際に直営農場で有機農業そして、究極の技術である不耕起栽培にも取り組んでいる。今回、この茨城県有機農業技術会議の松岡会長からお声がかかり、現地にお伺いして圃場を拝見し、今後の展開について意見交換をさせていただいた。
確かに現地に行くと、現在の日本の縮図のように、耕作放棄地が目立つ風景を目にする。水田は技術的な発展で、いまの水稲栽培は「革靴を履いていても代掻きから田植え、除草、収穫ができるといわれている」くらいに機械による作業一貫体系ができているので、機械の償却さえ可能であれば、昨今のコメ足りない騒動の中で、ほぼ耕作放棄地が見当たらない。しかし、畑のエリアは、特に地元農協が特産的な品目のブランド化戦略をとっていない地域にありがちな、何を作っていきたいのかよくわからない圃場が多くみられる。そして結果として耕作放棄地が目立ってきている。このような地域環境悪化のなかで、友部コモンズさんは、耕作放棄地を有機農業で再生というテーマを掲げ、まずは機械一貫体系を構築しやすい、有機大豆と有機麦の導入で土づくりを進めていきたいということである。
耕作放棄地を有機農業で取り組む醍醐味は、まさしく土のスピード感ある成長を肌で感じることができる。これに尽きる。特に耕耘機を入れたときに一番それが分かりやすいのに、なぜかこの土の状態を検証せず、土の炭素貯留率を上げるために不耕起でと考えられている。それは勿体ない。耕作放棄地ほど土が人の手で耕耘してくれるのを待っているのに、また、それによって、スピード感をもって応えてくれるのに、それは残念と代表の山神さんに話をした。山神さんは話に納得いただいて、特に不耕起にはこだわらないで、土の成長を一番に確認しながら様々な方法を試してみたいと、方針転換いただいたので、安心している。
有機栽培の技術は、不耕起が前提という考え方が日本の一部にあるが、それは正しくないと考えている。むしろ土が育ってきて、植物の根をいたわり育てられる能力がついてくれば不耕起でも十分栽培は可能になると思うが、それは技術ではなく、目標としての理想形の到達点である。それまでは、堆肥を活用して耕して、土の基礎地力を養い、物理性・化学性・生物性の要素をバランスよく成長させることに、あらゆる工夫を重ねるべきである。また、それを積み重ねる過程で、土が喜んで成長していくプロセスを、農業者の喜びとして共感して生きていける時間が存在するのだ。我が子の健やかな成長を喜ぶように。耕さない農業ではなく、耕さなくても作物が育つ土づくりを目指す。これが有機農業の本質である。
耕作放棄地を有機農業で取り組むことは、この喜びを日々味わえることである。この友部コモンズのような取り組みが、農業という枠組みを超えて、日本全国に広がることを夢見た訪問であった。
次号に続く