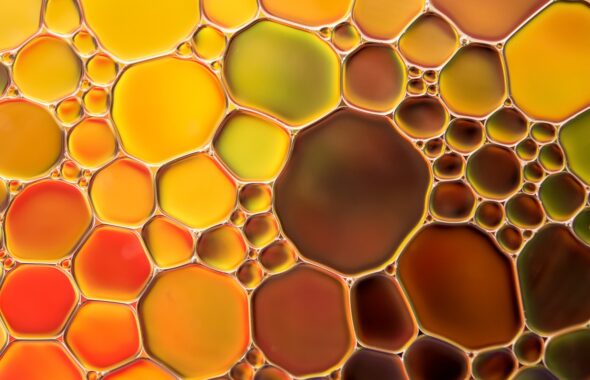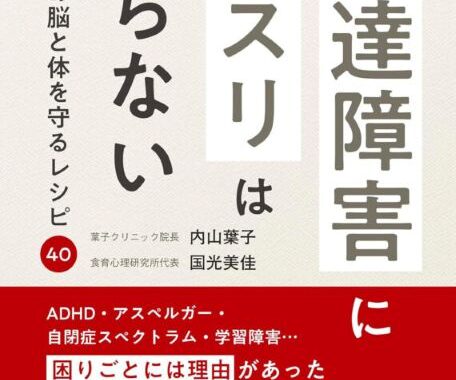緑肥としてのひまわりの抑草効果について
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.57
2025年9月 業務執行理事 南埜 幸信
土壌を肥沃化する目的で栽培され、腐熟させずに土壌にすき込まれる作物を緑肥作物という。緑肥作物の利用は古く、ヨーロッパではクローバーをすき込んだ後、小麦が栽培されていた。 アメリカではトウモロコシ栽培にアルファルファやダイズが緑肥として利用されていた 。日本でも、畑地では北海道の有機生産者で普及している小麦とアカクローバーの混播、ライ麦等、水田ではヘアリーベッチ、レンゲやソルガムが利用されてきた経緯がある。しかし、現金収入のない緑肥作物への関心は低いものであった。しかし近年、土づくりの取り組みが各地で進められており、特に有機農業では、土壌の基礎地力の向上ということで、長い目で見た土づくりのために、緑肥作物もその一つとして導入されてきている。
その効果は単なる粗大有機物としての機能だけではなく、有害線虫類の抑制、施設栽培土壌の塩類除去、病害・雑草防除等の土壌改良効果をもつことが明らかとなってきている。緑肥作物には多くの種類があり、イネ科(エンバク野生種、ソルガム、イタリアンライグラス、ギニアグラス)とマメ科(ヘアリーベッチ、アカクローバー、クロタラリア、レンゲ、セスバニア)を主体にキク科(マリーゴールド、ヒマワリ)やアブラナ科(シロカラシ)等が様々な用途で利用されている。
特にこの緑肥の効果として期待されるものについては、実は植物の発散するアレロパシー(他感物質)が大いに関与しているといわれ、特に雑草の抑制については、まさしく植物が自身の生活圏を守ろうとするためのアレロパシーが有効に働いていることが証明されてきている。
畑地および水田で利用されている緑肥作物は、粗大有機物としての機能、有害センチュ
ウ類の抑制、施設栽培土壌の塩類除去等の効果を期待されている。またそれに加えて、緑
肥作物には病害や雑草を抑制するアレロパシー作用(他感作用)を利用するという考えが
ある。植物のアレロパシーは 「植物が放出する化学物質が他の生物に阻害的あるいは促進的な何らかの作用を及ぼす現象」を意味する。アレロパシーの作用経路は次の4つある
と提唱されている:1)葉から雨、露あるいは霧によって浸出される(leaching) 、2)代謝産物が揮発性物質として放出される (volatization)、 3) 植物体の残渣 ( litter) 、
4)根から分泌する物質(exudation)。そして特に3)はさらに
①落葉から物質が浸出される場合
②落葉や腐葉が分解して他感物質に変化する場合
③残根やちぎれた根が分解する場合の3つに分けられている。
私は今年の一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの事業の一つに、油脂用ひまわりを有機農業の土づくりの輪作として導入し、有機の国産油脂を供給していく道筋をつけることと、緑肥でありながら換金性があり、輪作として導入する経済的なメリットのあるひまわりに注目して、取り組みを進めてきている。その取り組みには、一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの内部でも批判的な意見もある中で、沖縄県や千葉県の有機の生産者で、南埜がそんなに言うのであればと、導入試験に取り組んでいただいた貴重な生産者がいる。猛暑と雨不足の中でも順調に生育し、先日開花全盛の圃場にお伺いして、実は驚きとこのひまわり導入の推進について核心的な状況に出会い、大きな希望を得たことをここに報告したい。
ひまわり畑は雑草がたいへん少ないのだ。同じ生産者が今年から種子の確保に取り組んで隣の畑で栽培している「たかきび」はかなり雑草に負け始めているのに、ひまわり畑にはほとんど雑草が無い。雑草抑制効果は、特に除草が大きな技術的なテーマになる有機農業では、重要な導入動機になる。これは国産の有機油をという目的だけではなく、有機農業での推奨される輪作体系のモデルにもあると、久しぶりの興奮を覚えている。かねてよりひまわりには、土壌が吸着して植物が吸収できなくなっているリン酸を、土壌から遊離し、吸収できるものに変えるちからのある根圏微生物のアーバスキュラー菌根菌との共生力の高さが評価されていて、それだけでも、特に火山灰土壌の多い日本では、導入の効果が期待されていた。ここでさらに、雑草抑制効果が高いということになると、有機農業についてのメリットもさらに際立ってくる。
そこでさっそく、日本のアレロパシー研究の第一人者である、東京農工大学の名誉教授の藤井先生に連絡してみたら、さらに驚くべき返事をいただいた。世界にはこのヒマワリのアレロパシーについての研究が多くあり、実に雑草を抑制する効果については、研究が進み、成分の特定もできているということである。藤井先生の手元にある論文をさっそく送ってくださるということ。これを来春までに整理して、課題である油脂用の種子の導入も進めて、有機農業の土づくりの加速と、有機農業による国産油脂の確保とをテーマにした、輪作でのひまわり導入を積極的に生産者に提案していきたいと考えている。
(参考資料)**農林水産省『緑肥の効果について』
次号に続く