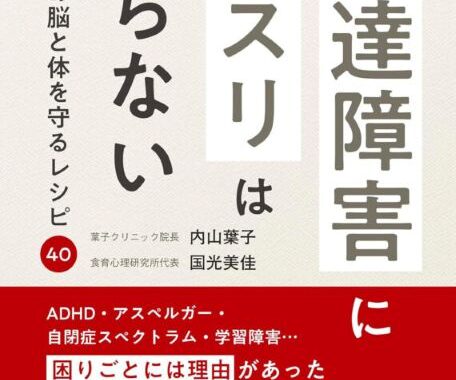国産有機小麦の展開について
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.56
2025年9月 業務執行理事 南埜 幸信
国産有機小麦の展開について、現状の課題を整理したい。まず、生産地の課題としては、やはり反収の低さであろう。収量が低い分、同じ売り上げと収益を生産者にということになると、どうしても単価が高くならざるを得ない。個人的には慣行の生産者と肩を並べるくらいの収量を上げる生産者も出てきたことは大いなる希望の灯りは見えてきているが、平均としては、慣行の生産者のレベルからすると、かなり低いということになっているので、生産者からの買い入れ価格がかなり高くなってしまっている現状である。私などは、有機の野菜のマーケットで長く仕事をしてきて、現実的には慣行と有機の価格差は2~3割高ということでマーケットの拡大を進めてきたところなので、正直言って、有機穀物の世界に入ってみて、この価格差には驚いている。逆に、これを普及拡大するにはまず、この価格差をどのように埋めていくのかということが、何をおいても一番の仕事と理解している。
この価格差の要因は何かと考えたときに、まずは前述の単位当たりの収量が低いということであろう。多くの生産者の意見をうかがっていると、これは、家畜の糞尿などの養分系(肥料供給系)の堆肥の投入量を増やし、特に窒素成分をもう少し多く施用することによって反収とグルテンが増やせると考えているのだが、逆に窒素肥料の追加は、生育期間中、特に登熟期のムレによって小麦の大敵の赤カビの発生を助長するのではというリスクが増えてくるというのである。つまり反収の増加と、病害の発生はトレードオフの関係にあり、ちょうどよい収量レベルを前提にしないということに落ち着く。特に近年は、小麦の収穫時期の6月~7月は、全国的に集中豪雨や異常降雨という現象に見舞われ、この赤カビ発生のリスクが高まっていることも考慮しなければならない問題である。
次に考えなければならないのは、製粉工程のコストである。特に小麦粉の製粉については、確実に規模の経済が働き、一回の製粉は可能な限り大きいロットを投入したほうが歩留まりは良くなる。その理由は、ここで歩留まりを悪くする最大の原因は、製粉ラインに残ってしまう原料の残留と、一般慣行品との区分管理のための共洗いという工程になる。つまり、有機ならではの区分管理コストということになる。加えて、有機の製粉作業については、前後の作業で、慣行品の約2倍の作業時間が必要となるといわれている。作業時間の増大はまさしくコストの増大ということになる。
さらには、原料の保管、輸送等のハンドリングでも、有機の専用保管エリアを設けたり、作業記録等の内部規定上の定められた記録を残したり等、区分管理コストが重なっていく。
原料価格がそもそも高い上に、さらに区分管理コストという、有機ならではのコストがかかることで、有機小麦粉と一般の価格差が広がってしまっていることが、有機小麦の普及のネックとなっていることがご理解いただけたのではないかと思う。
では、この価格差をどのように埋めていくか。これは単なる生産者だけの問題ではなく、生産者から保管問屋、製粉メーカー、加工品製造メーカー等、バリューチェーン全体で課題を共有し、時には有機に向く、あるいは病害虫に強い品種改良や、有機栽培技術研究についての政府の専門研究機関や、有機に向いた、あるいは有機専用ラインの常設できる加工施設の整備のための国の支援、あるいは、有機穀物生産者への、特に体力のない有機転換期間中の生産者への支援の強化を農水省にさらにお願いしていく等、国として有機小麦生産者の拡大政策を策定していくことをお願いしていく必要があると痛感している。
次号に続く