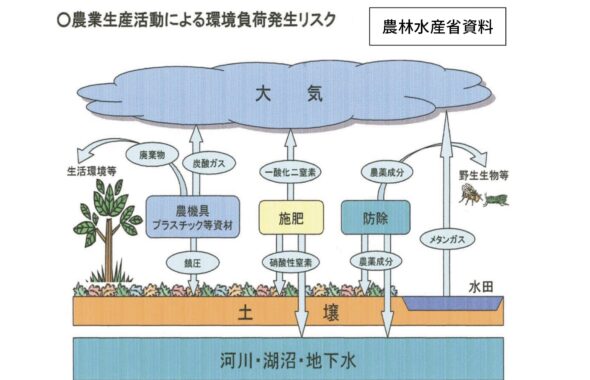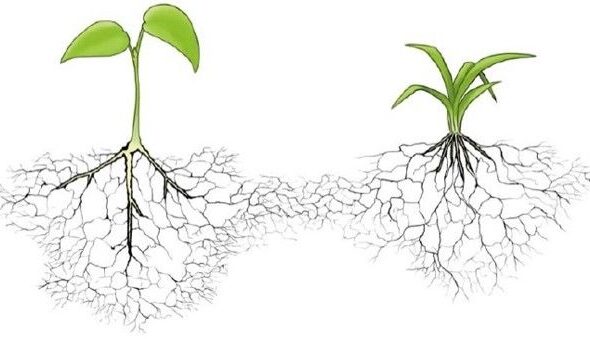みどりの食料システム戦略誕生の背景 Farm to Fork vol.3
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.17
2024年12月 業務執行理事 南埜 幸信
持続可能な⾷品消費および健康的で持続可能な⾷⽣活への移⾏の推進
フードチェーンで、最も川下に位置するのが消費者だ。FTF戦略では、その消費活動にも切り込んだ。その前提として、EUでの消費の現状について、
- ⾚⾝⾁(⽜⾁、⽺⾁、豚⾁など)や砂糖、塩、脂質の平均摂取量は、推奨値を超えている。
- 対して、穀物や果物、野菜、ナッツ類などの消費は不⼗分で、環境・健康の両⾯で持続可能性が低い。
と指摘した。その上で、欧州委として、⾷品消費の持続可能性を⾼めるため、以下の2つの⽬標を提起した。
第1は、2030年までにEU内における肥満率を減少に転じさせることだ。具体的には、加⼯⾁や⾚⾝⾁の消費を減らし、植物中⼼の⾷⽣活への移⾏を促進させることで、疾病リスクや環境への影響を軽減するとした。
第2に、消費者が正しい情報に基づき、健康的で持続可能な⾷品を選べるようにすることだ。これは⼈々の健康と⽣活の質を上げるとともに、健康維持に要する費⽤の削減にもつながるとした。
これらの⽬標の達成に向けて、欧州委が提起しているのは下記のとおりだ。
- ⾷品包装の表⾯(front-of-pack)での栄養素表⽰の義務化
- 原産地表⽰の対象拡⼤の検討(現在は豚⾁や鶏⾁などの特定の⾷品のみが対象)
- 気候変動、環境、社会的側⾯などに関する⾃主的な表⽰の枠組みの作成
- ⽬が不⾃由な⼈々の⾷品情報へのアクセスの改善
- 学校や病院の給⾷サービスにおける持続可能な⾷品調達に関する最低義務基準の設定
- 有機野菜などに対する付加価値税の軽減など 税制上の優遇措置の導⼊
⾷品ロスおよび廃棄の削減など
⾷品廃棄の削減も⼆酸化炭素の排出減に⼤きく寄与できる取り組みの1つだ。2030年までに⼩売店・消費者レベルで の1⼈当たり⾷品廃棄を半減させるという⽬標を掲げ、達成のために「⾷品廃棄の削減に関する法的拘束⼒のある⽬標の設定」「『消費期限』と『賞味期限』の誤認・誤⽤を防ぐためのルール改正」「⽣産段階における⾷品ロスの調査と 対策の提案」といった措置を講ずるとした。
また、消費者を欺き、正しい情報の⼊⼿を阻害する詐欺的⾏為は、フードシステムの持続可能性を妨げる。このことから、欧州委は欧州刑事警察機構や業界団体などの関係機関とも協⼒し、⾷品に関する詐欺⾏為に対する取り締まりを強化するともした。
世界的な移⾏を⽬指して
欧州委は以上のような持続可能なフードシステムへの円滑な移⾏を実現するため、「調査・投資」と「助⾔・知⾒の共 有」という⼤きく2つの⽀援措置を掲げる。前者に関しては、欧州グリーン・ディール政策の下で、既に2020年に10 億ユーロの拠出を予定。後者については、持続可能性に関する客観的で的確なデータを⾷料品関係者に提供するための システム構築を進めるとしている。
FTF戦略は、EUのフードシステムを持続可能なものへと移⾏させるにとどまらない。戦略では、国連の「持続可能な開 発⽬標(SDGs)」を踏まえ、世界的な移⾏をEUが主導することをうたう。価値観を共有する全てのパートナーとの「グリーン同盟」を⽬指すとしているのだ。具体的には、EUとの間で締結される全ての⼆国間通商協定の中に、野⼼的な持続可能性に関する章(chapter)を含めることを求めていくとした。
また、EUの貿易政策を通じて、動物福祉、農薬の使⽤、抗⽣物質耐性といった分野における第三国との協⼒を強化し、第三国からも意欲的なコミットメントを得るという。加えて、⾷品分野の研究と技術⾰ 新で国際協⼒に注⼒することも盛り込まれた。特に気候変動の緩和と適応、持続可能な景観と⼟地の管理、環境保護と 持続可能な⽣態系の活⽤といった分野を例⽰している。さらには、世界的な森林破壊に対するEUの関与を減らすため、欧州委は2021年に森林破壊に関与している製品のEU市場への投⼊を防ぐ(または最⼩化する)ための法制度を提案するとした。
漁業分野でも、既に制度化している違法・未報告・未制限(IUU)な漁業に対する規制の厳格化と、持続可能な⽔産資源管理の推進などを掲げている。
上述の通り、FTF戦略には、栄養プロファイル制度の導⼊や栄養成分のパッケージ表⾯への表⽰義務化など、EUに⾷品 を輸出する⽇本企業も今後対応が求められるであろう内容が含まれる。そのほか、動物福祉や持続可能性への配慮など、フードシステムの根本的な価値観に関わる内容も多い。仮に環境フットプリントの削減が⾷品事業者に義務付けられれば、そもそも「遠隔地から⾷品を輸⼊する」という⾏為⾃体が制約を受ける可能性もある。
EUが「世界的な移⾏」をどこまで主導できるかは、現時点では計り得ない。ただ、中⻑期的な持続可能性という点において、われわれの依拠するフードシステムに⻩信号がともっていることも確かだ。EUが打ち出す対策いかんにかかわらず、国内の⾷品産業における環境・持続可能性・動物福祉といった価値観に対する意識をこれまで以上に⾼めていくことが必要な時代が来たと考える。
もはや猶予はない。
次号に続く